「子どもの好きな遊びを、できるだけ伸ばしてあげたい」そう願うママ・パパは多いはずです。
中でも、レゴブロックは長年愛されている定番の知育おもちゃ。
カチッとはめるだけのシンプルな構造ながら、無限の可能性を秘めていて、遊びの中で自然と創造力や集中力、論理的思考などが育まれていきます。
また、「東京大学の学生の約7割が幼少期にレゴでよく遊んでいた」という調査結果もあり、子どもの将来の可能性を広げる遊びとして改めて注目されています。

私の5歳の息子もレゴが大好きで、最近では乗り物シリーズやマイクラシリーズに大ハマりしています。
本記事では、レゴが子どもに与える良い影響やメリット・デメリット、遊び方の工夫などを、わかりやすくご紹介していきますね。
子供の「レゴ好き」を、もっと自信をもって見守れるようになるヒントになれば幸いです。
レゴとは?

レゴ(LEGO)とは、デンマーク生まれのプラスチック製ブロック玩具で、1930年代に登場して以来、世界中の子供から大人まで幅広く親しまれています。
レゴ(LEGO)の語源は、デンマーク語で「よく遊べ(leg godt)」という言葉から来ています。
小さなブロックを自由に組み合わせて建物や乗り物、キャラクターなどを作れることが特徴で、教育玩具としての側面も強く、世界中の教育現場や知育玩具としても活用されています。
レゴの魅力

レゴの最大の魅力は「自由度の高さ」と「創造の可能性」です。
マニュアル通りに組み立てることもできますが、自分だけのオリジナル作品を作ることもでき、遊びの幅が無限に広がります。
また、レゴにはシリーズが豊富にあり、「レゴシティ」「レゴフレンズ」「レゴテクニック」「レゴデュプロ」など、年齢や興味に合わせて選べるのも人気の理由です。
子供だけでなく、大人向けのコレクションや建築モデルもあるため、年齢を問わず長く楽しめる点も魅力の1つです。

ちなみに……
我が家の息子(6)は、主にレゴシティー、娘(13)は、レゴフレンズ・どうぶつの森シリーズが大好きです。
レゴのメリット|子供に与える良い影響

レゴは、ただの遊び道具にとどまらず、子供の発達においてたくさんの良い影響をもたらす「知育ツール」でもあります。
遊んでいるだけなのに、自然と力が育まれていく不思議な魅力について、詳しく解説していきます。
創造力と想像力をぐんぐん育てる

レゴには、正解がありません。お城を作ってもいいし、動物を作っても良いし、乗り物を作ってもいい。
ブロックをどうやって組み立てるか、何を作るかは全て子供次第です。
自由な発想で形を作る過程は、創造力と想像力を大きく刺激します。
また、興味深い調査として「東京大学の学生の約7割が、幼少期にレゴで遊んでいた」というデータがあります(参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000032313.html)。
大人になっても、思考や論理性を発揮しているというのはなんといっても興味深いですよね。
上記のことからも「遊び=学び」として、レゴが良質な土台を育ててくれていると考えられます。
問題解決能力が自然と身に付く

「どうやったらここがくっつくかな?」「土台がグラグラするから、どう直そう?」などレゴ遊びは小さな問題がつきものです。
それを自分で解決していく経験が、子供の中に「工夫する力」や「考える力」を育ててくれます。
私の息子は、以前は「出来ないからもういい!」と、投げ出しがちでしたが、日々の組み立てを通して「あきらめない力」がグンと伸びたように感じます。
失敗してもやり直せる、壊れてもまた作れる、レゴだからこそ試行錯誤を楽しみながら、柔軟な思考とチャレンジ精神の向上へと導きます。
集中力と忍耐力を遊びの中で強化される

初めのうちは数分で飽きてしまっていた子供が、「いつの間にか1時間も集中して組み立てていた」そんな経験がある方も少なくないですよね。
小さなブロックを何度も重ねたり、パーツを探したり、完成までにやり切るには集中力と根気が必要です。
しかしそれらを「やらされる」のではなく「好きだから夢中でやっている」状態が続くのがレゴのすごいところ。
自然と集中力と忍耐力や達成感も育まれていきます。
空間認識能力や論理的思考の基礎作り

立体的なものを組み立てる作業は、空間を把握する力や順序立てて考える力を養ってくれます。
どのブロックをどこに組み合わせるか、完成図を頭に思い描きながら作っていくうちに、図形の感覚や構造をとらえる力が自然と身についていきます。
これらは、のちに算数や理科、プログラミングなどの学とも深く関わってくる部分です。
レゴのデメリット|与えすぎには注意

レゴにはたくさんの魅力がありますが、子どもに与えるときには「量」や「使い方」に気をつけたい点もあります。
良いものだからこそ、バランスを意識することが大切です。
遊びの時間を管理する

レゴは夢中になりやすいおもちゃだからこそ、「気がつけば何時間も遊んでいた……。」なんてことも珍しくありません。
集中することは良いことですが、長時間にわたって同じ姿勢でいると身体への負担や、目の疲れなどが心配です。
また、レゴばかりに熱中してしまい、外遊びや他の活動が少なくなってしまうのも避けたいところです。
「今日は何時までね」「お昼ご飯の後にしようね」と、時間を区切っておくことで生活リズムも整いやすくなります。
他の遊びや学習とのバランスを取る

レゴに限らず、ひとつの事だけに偏ってしまうと経験できることが限られてしまう可能性も出てきます。
自然の中で遊んだり、読書をしたり、友達と関わったりすることも子供にとっては大切な学びです。
さまざまな遊びの中のひとつとしてレゴを取り入れることで、より豊かな成長につながります。

レゴが好きなうちの子、他のことにも興味を持ってくれるかな……。
と、心配になることもあるかもしれませんが、無理に引き離すよりも、上手に「つなげる」工夫がおすすめです。
例えば、「ブロックで作ったお店を絵に描いてみようか?」「公園にある遊具をレゴで作ってみよう!」など、他の活動とレゴを連携させることで、より幅広い力を伸ばすことができます。
レゴが好きな子の特徴

レゴ遊びに夢中になる子どもには、単なる“おもちゃ好き”では済まされない、奥深い特性が隠れていることがあります。
実際に遊ぶ様子をじっくり観察すると、「この子、こんな力を持っていたんだ」とハッとする場面があるかもしれません。
ここでは、そんなレゴ好きな子どもたちに多く見られる特徴を、少し掘り下げてご紹介します。
1. 好奇心旺盛で、試すことを楽しめる探究心がある
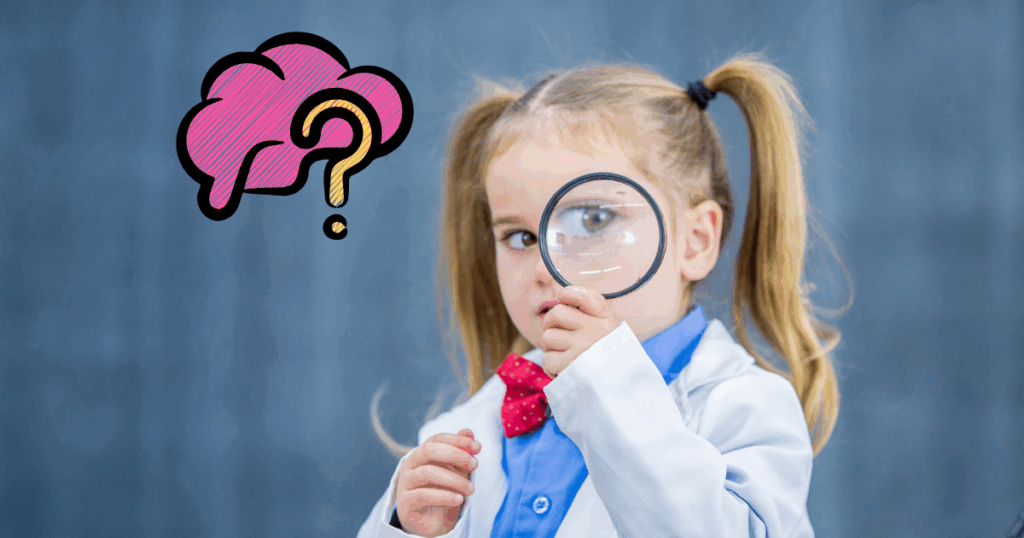
新しいブロックやテーマセットを見ると、目を輝かせて「これ何?どうやって組むの?」とすぐに手を伸ばす姿は、まさに“学びの原点”です。
子どもなりに試行錯誤しながら、何度も組み替えては「違うな……」「こっちの方がいいかも」と工夫を重ねていく様子には、自然な探究心があふれています。
これは将来、理系・文系を問わず学びに向かう力の土台になる貴重な資質です。
2. 細部に目が行き届く繊細さと、コツコツ積み上げる力がある

レゴは決して大きな動きのある遊びではありませんよね。
それでも長時間、じっと小さなパーツと向き合いながら、ひとつひとつ丁寧に組み上げていく子どもは、手先の器用さだけでなく、物事に集中して取り組む“根気”を備えています。
とくに手順を守って正確に再現することを好む子は、几帳面な気質や高い自己管理能力が育っている可能性があります。
3. 1つのことに没頭できる集中力を持っている

気づいたら1時間、2時間とブロックに夢中になっている……。そんな様子に驚いた経験はありませんか?
これは、好きなことに対して強い“没入力”がある証拠です。
集中力が高い子は、ほかの場面でも自分の世界に深く入り込む力があり、将来的に何かに専門的に取り組む場面でも大いに役立ちます。
デジタルに囲まれ、注意が散りやすい現代だからこそ、この集中力はとても貴重です。
4. 発想が自由で、独自の世界を形にする想像力がある

設計図通りに組み立てるだけでなく、「こんな塔を作ったよ」「これは宇宙のおうちなの」と、子どもなりの物語やイメージをレゴで形にしようとする姿には、大人がはっとさせられるような創造性が潜んでいます。
子供はまだ言葉では説明できなくても、頭の中にある世界を「形」にする力を持っています。
その創造力は、美術・デザインだけでなく、未来の課題解決力や発想力にもつながっていくでしょう。
力をどう伸ばしてあげられる?

レゴに夢中になる子どもを見て、「楽しそうだな」と微笑ましく思う反面、「これって将来につながるのかな?」と少し不安になることもあるかもしれません。
しかし、子どもが夢中になっていることには、必ず理由があります。
そこには集中力や創造力、考える力など、人生を支える土台が育まれているのです。
そんな子どもの力を、もっと伸ばしてあげるために、家庭でできることをいくつかご紹介します。
1. 自由な発想を尊重し、「すごいね」と認めてあげる

「えっ、これ何を作ったの?」と大人には分からないものでも、子どもにとっては立派な“作品”です。
たとえば「この部分が飛び出しているのは、わざと?」と聞いてみると、「うん、ここからミサイルが出るんだよ!」とワクワクしながら説明してくれるかもしれません。
このように、作品の完成度ではなく「工夫した部分」「考えたプロセス」に注目して声をかけることが、子どもの自己肯定感や発想力を大きく育てていきます。
2. 一緒に遊ぶ時間を通して、会話のきっかけを作る

「ねえ、これなに作ってるの?」「ここ手伝ってもいい?」と、軽く声をかけるだけで、子どもは嬉しそうに話してくれることが多いです。
一緒にブロックを組む時間は、単なる遊びではなく、親子の心がつながる大切なコミュニケーションの時間。
子どもは「自分の好きなことに、親が関心を持ってくれている」と感じると、さらに安心してのびのびと創造力を発揮するようになります。
3. 本や展示など、興味の幅を広げられる環境に触れさせる

レゴに関する図鑑や写真集、公式のレゴ展やレゴランドなどに足を運んでみると、目の前の世界がぐっと広がります。
実際にプロが作った作品や、他の子どもたちの創作を見ることで、「自分もこんなの作ってみたい!」という刺激を受け、創造力がより深まります。
また、図鑑を通じて建築や宇宙、恐竜、ロボットなどテーマへの興味が広がることもあり、学びの入り口としてもとても効果的です。
4. レゴ教室やワークショップに参加させてみる
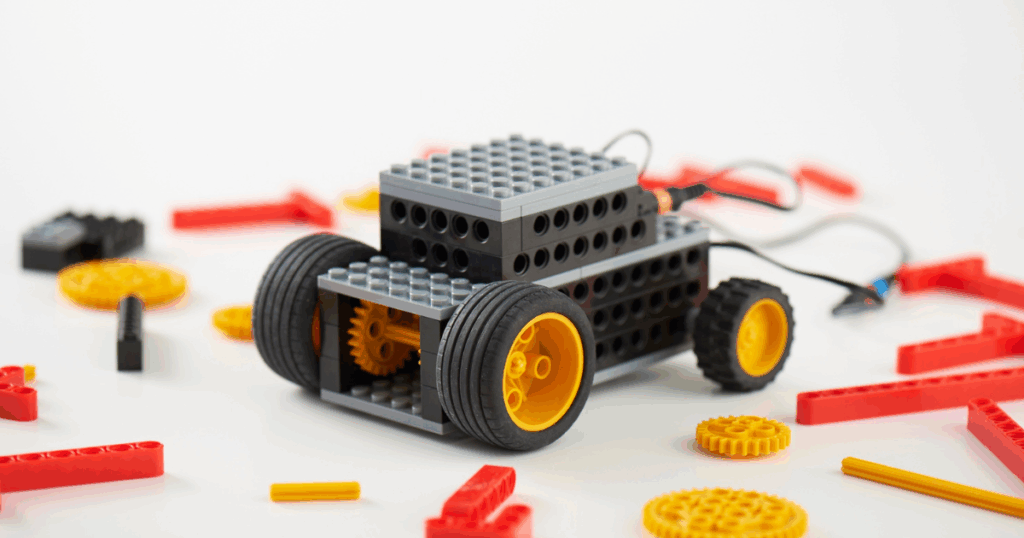
近年では、レゴを使ってプログラミングや論理的思考を学ぶ教室も増えていて、仲間と一緒に課題に取り組む中で、協調性やプレゼン力が育まれる場にもなります。
また、「家ではついワンパターンの遊びになってしまう……。」という悩みを持つご家庭にも、外部の刺激はとても有効です。
同じ興味を持つ仲間と出会えることも、子どもにとって大きな自信になります。
レゴを使った遊びのアイデア
レゴは、工夫次第でただの組み立て遊びから「学びの宝庫」に変わります。
遊び方にちょっとした工夫を加えることで、創造力や集中力、コミュニケーション力など、子どもの成長に欠かせない力が自然と育まれます。
「同じパーツばかりで飽きてきたかも……。」というときも、視点を変えるだけで遊びの幅はぐっと広がります。
ここでは、親子で楽しめるレゴの遊び方のアイデアを具体的にご紹介します。
【あそび×くふう レゴゲーム 50のアイデア】(著:大野 千鶴/訳)は、家庭で楽しめるレゴ遊びを50種類紹介しているおすすめの本です。
ストーリーを作って遊ぶ(ごっこ遊び×創作力)

「これはプリンセスが住んでいるお城だよ」「このロボットは宇宙から来たんだ!」など、作った作品にストーリーをつけて遊ぶことで、子供の想像力や表現力が豊かになります。
ママやパパが「その子はどんな名前?」「このあと何が起きたの?」と少し質問するだけでも、子供の思考がどんどん膨らみます。
言葉で物語を語る力や、他者に伝える練習にもなるので、コミュニケーション能力の発達にも◎。
模倣遊び(身の回りの世界を再現)

家の近くのスーパー、リビングのテーブル、乗ったことのある電車やバスなど、身近なものをレゴで再現してみる遊びもおすすめです。
「これ、さっき公園で見たすべり台だね!」という気づきがあると、観察力や記憶力が養われます。
親子で一緒に「どうやって再現する?」と話しながら作ることで、構造やパーツの使い方も学べて、小学生になってから図工や理科で必要となる「形を見る力」にもつながります。
制限時間チャレンジ(楽しく集中力アップ)

「5分でおうちを作ってみよう!」「10分で一番高いタワーを作れるかな?」など、あえて時間制限をつけて遊ぶチャレンジです。
時間が限られている中で試行錯誤することで、集中力や判断力、計画性も育ちます。
うまくいかなくても「次はこうしてみよう」と考える力が養われるので、ゲーム感覚で取り入れると盛り上がります。
兄弟姉妹やお友達と競争する場合は、「すごいね」「これもいいね」とお互いを褒め合う声かけを意識すると、協調性やポジティブな自己肯定感にもつながります。
「いつも同じ遊び方で飽きちゃう」という声もよく聞きますが、少しのアレンジでレゴの世界はぐんと広がります。
子供の発想に大人が乗っかる形で関わると、親子の対話も自然に生まれて、かけがえのない時間になります。
年齢別のレゴ活用法

うちの子、どんなふうにレゴと関わっていけば良いんだろう
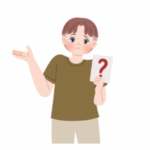
今の年齢にあった遊び方ってあるのかな?
子供の成長段階によって楽しみ方や伸びる力は少しずつ変わってきます。
この章では、幼少期から小学生の子供に向けて年齢別のおすすめのレゴシリーズをご紹介します。
3歳|はじめての組み立て
3歳頃は、手先の器用さが急成長するタイミングです。
大きめのブロック(LEGO デュプロ)を使って、ブロック同士を「つなぐ」「外す」などの基本的な操作を通じて、指先と目の連携(=ハンドアイコーディネーション)を育てます。
- 手指の発達
- 色・形の認識
- 集中力の芽生え
「赤いブロックを取ってみよう」「高く積めるかな?」など、言葉がけで遊びを広げてあげると、認知力も伸びやすくなります。
4歳|形と色から想像を広げる「ミニストーリー作り」
4歳になると、「何かに見立てる」力が育ってきます。
例えば、「これが車で、ここがおうち!」といった、簡単なストーリーを含む作品が自然と生まれてくるので、遊びが“創造”へとシフトし始める大事な時期です。
- 想像力
- 言葉の発達(ストーリーを語る力)
- 空間認識
「この人はどこに行くの?」「何が起こるのかな?」など、子どもの想像を広げる質問で会話を楽しんでみましょう。
5歳|構造への興味が深まる「試して覚える」時期
5歳頃になると、作品に“目的”を持たせ始めます。
たとえば、「車が坂道を走れるようにしたい」「屋根が落ちないようにするには?」など、構造的な思考が芽生えてくるのが特徴です。
- 問題解決能力
- 構造的思考
- 持続力(完成まで取り組む
「坂道をつくるには何が必要かな?」など、ちょっとしたヒントだけを与え、あとは見守るスタンスが◎。
6歳|設計から完成まで「自分の世界をかたちにする」
6歳頃は、自分の中のイメージを具体的に組み立てる力が飛躍的に伸びます。
「設計図を描く→組み立てる→直す」というプロセスを経て、自主性・論理的思考・完成への意欲が育っていきます。
さらに、説明書通りに組み立てることも可能になってくるので、大作に挑戦してみるのもおすすめ。
- 論理的思考(順序立てて組む)
- 自主性・達成感
- プレゼン力(作品を説明する力)
「説明書を読んで自分で作る」体験を尊重して、完成後は「すごいね、ここはどうやって組み立てたの?」と聞いてあげると、自己肯定感アップにも繋がります。
レゴ教室の活用

レゴは「遊び」の枠を超え、今や教育の現場でも注目されています。
レゴブロックを使ってプログラミングや理数的思考を学ぶ「レゴ教室(レゴスクール・STEM教室)」では、専門のカリキュラムに沿って、子どもたちの創造力・論理力・問題解決力をぐんぐん育てることができます。
レゴ教室ってどんなところ?

レゴ教室(レゴスクール・STEM系教室)では、年齢や発達段階に応じたプログラムのもと、子どもたちが「考えて、作って、発表する」サイクルを楽しみながら学んでいます。
対象年齢は幼稚園年中〜小学生までの、カリキュラムが整っています。
また、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)を取り入れた教室も増えており、レゴ×教育の可能性はますます広がっています。
学習支援システム LEGO Education
まとめ

レゴは、単なるおもちゃにとどまらず、創造力・集中力・問題解決能力・空間認識といった、子供の将来につながる重要な力を遊びながら育むことができる貴重な知育ツールです。
特に、東京大学の学生の多くが幼少期にレゴで遊んでいたという調査結果からもわかるように、レゴを通じた体験は、学力だけでなく、学びへの姿勢や思考力の土台作りにも影響を与えていることがわかります。
とはいえ、レゴに限らず、どんな遊びもバランスが大切です。レゴの魅力を活かしつつ、日常の中でさまざまな体験や遊びを取り入れることで、子供はより豊かに成長していくことでしょう。
レゴを通して、子供の可能性を広げ、未来への力を育んでいきましょう。








コメント